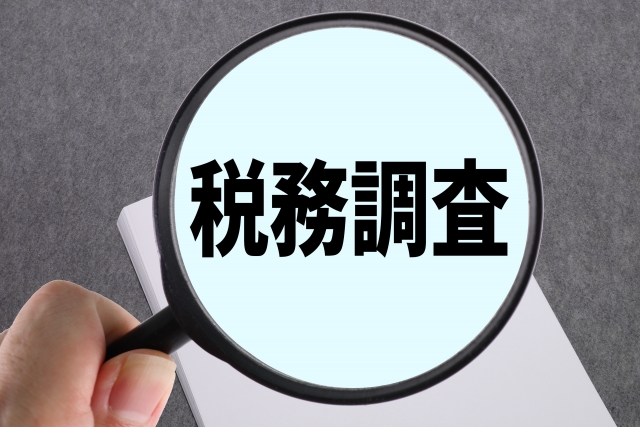【はじめに】
私は、主に法人税の仕事をしてきたためか、所得税が不思議な取り扱いになっていると思うことが多々あります。
所得税法は、きれいに書かれているのに、取り扱いで混迷してしまっているような気がしてならないのです。
原因として考えられるのは、様々な立場の人に対して、あまねく同じ所得に同じに税負担をしてもらう困難さがあるのかもしれません。
まずは、次の「1.【法律】」の全体を読み、太字部分に注目してください。
1.【法律】
所得税法第37条(必要経費)
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。


【解説】
上記所得税法第37条は、「総収入を得るために直接要した費用の額(いわゆる『原価』)と、費用のうち償却費以外で債務の確定したものが必要経費に入りますよ」と明らかにしています。
ここで、「総収入を得るために、直接要した費用」は、必要経費に入ることが明らかで、債務の確定は、必要経費の要件に入っていないません。
それを踏まえて、次の所得税基本通達をご確認ください。
【通達】
所得税基本通達37‐1(売上原価等の費用の範囲)
法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。


【解説】
所得税法では、総収入金額を得るため直接に要した費用の額とされているのに、通達で債務の確定しているものに限ると、さらに制限をかけてしまっています。
具体的には、大工さんが建設工事を請け負って、建物が完成して施主に引き渡したが、門塀の工事がまだ終わっていないような場合、門塀の工事原価を必要経費に入れられるかというケースです。
所得税法では、直接要した費用の額とされており、「要する」ではなく「要した」という過去形の表現から、法人税法の「収益に係る売上原価(法人税法22(3)一)」よりもやや限定的な書きぶりであるとは評価されます。
しかしながら、法律で債務の確定とまでは記載されていないのに、通達で制限を設けてしまっているようにも読めてしまいます。
ただ、通達も「ものとする」と、やや含みを残した書き方をしているので、原則的な考え方を示しているにすぎないのかもしれません。